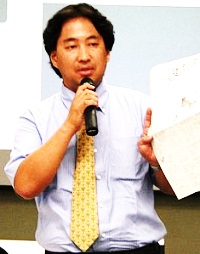今回の研修会では、神戸大学のリチャード・ハリソン先生と實平雅夫先生のお二人を講師にお招きし、「能動的学習を促す学習環境デザインと教材作成」というテーマでお話いただきました。
日時 : 〈台北会場〉2007 年9月1日(土) 10:00~17:00
2日(日) 10:00~16:45
〈台中会場〉2007 年9月4日(火) 10:00~17:00
〈高雄会場〉2007 年9月6日(木) 10:00~17:00
7日(金) 10:00~16:45
参加者 : 台湾の日本語教育関係者 (台北)34名 (台中)34名 (高雄)40名
配布資料: 「能動的学習を促す学習環境デザインと教材作成」(PDFファイル)
関連資料: リチャード・ハリソン、實平雅夫(2005)「教育理念を具体化するFlexible
Classroom(I) : 日本語教育CALL環境の設計・導入」『神戸大学留学生センター紀要』11、55-73
リチャード・ハリソン、實平雅夫(2007)「教育理念を具体化するFlexible
Classroom(II) : 学習効果の評価に基づく日本語教育CALL環境の再設計と再評価 」『神戸大学留学生センター紀要』13、21-33
まず初めに、今回のテーマにもなっている「能動的学習」とは何か、「学習環境」とは何かについて、日本語学習の場でよくありがちな教師、学習者を例に取り、どこに問題があるのか、何を変える必要があるのか、またそのために何をすべきなのかについて提示されました。
次に、教育の現場で常に問題となる「理想」と「現実」について、神戸大学での実践例が報告されました。学校もしくは教師が考える理想を実現することは容易ではないが、実践に向けてまず動いてみること、また実践するに留まらず、それらを評価し、次の授業に生かしていくといった、一連のサイクルとして継続することが 重要であると強調されました。またその考えを裏付ける論拠として、社会構成主義に関する理論を取り上げ、日本語教育と社会構成主義の関連についての最新動向なども随時紹介されました。
更に講義内容を受け、デジタルビデオを教材として、能動的学習の要素を取り入れた教案を作成するワークショップをグループごとに行いました。教師が与えるのではなく、学習者が能動的に学習するにはどんな活動が適切であるか、参加者が普段行っている授業を振り返りながら、アイデアを搾り出す作業を行いました。
それぞれのグループが作成した教案を発表し、講師の先生方だけでなく、参加者からもフィードバックを募り、アイデアを評価しあいました。他の先生方のアイデアを実際に見聞きすることで、お互いに刺激になり、参加者からも「勉強になった」との声が多数聞かれました。
最後に、模擬授業として、参加者自身が学習者となり實平先生が実際に日本事情の授業で行っているインタビュー形式のデジタルビデオク
リップを作成し、ビデオ映像の簡単な取り込みと編集の方法を体験しました。活発な活動を取り入れることで、教員の立場だけでなく、学習者としてなど様々な角度から授業を見直す契機を与えられる研修会となりました。
リチャード・ハリソン先生 實平雅夫先生