去る8月28日から9月3日にかけて2005年度日本語教育夏期研修会が開催されました。今回の研修会では、広島大学大学院教育学研究科助教授である横溝紳一郎氏と柳瀬陽介氏のお二人を招き、「教室内での教師のことば-理論と実践」というテーマのもと、講義とワークショップを行いました。
日時:〈台北会場〉2005 年8月28日(日)9:00~16:30・29日(月)9:00~15:30
〈台中会場〉2005 年8月31日(水)9:00~16:30
〈高雄会場〉2005 年9月 2日(金)9:00~16:30・3日(土)9:00~15:30
参加者:台湾の日本語教育機関で日本語を教えている教師
(台北)49名 (台中)21名 (高雄)53名
配布資料: 横溝先生のプリント 「ティーチャートークと媒介語使用」
柳瀬先生のプリント 「授業分析」「実践研究」
(上記資料はPDFファイルですのでAcrobat Readerが必要です)
研修会では、まず横溝先生による講義から入り、JFL(Japanese as a Foreign Language)とJSL(Japanese as a Second Language)の違いという観点から、コース体系や学習者のニーズ、学習環境の違いなどについての説明があり、それぞれの適切な教え方、さらには教室での媒介語使用についてのお話がありました。受講生は講義の最初から、「いい日本語の先生とは?」というタスクを与えられ、自分の日本語教育でのビリーフス(信条)を考えさせられました。次に柳瀬先生の英語教育の分野から見た「授業分析」について講義があり、実際の日本の中学校や高校で行われている英語の授業のDVDを見ながら、そこでの授業方法の特徴を観察しました。英語の授業から日本語教育へ応用できる活動などが多々あり、同じ外国語教育にたずさわる者として学ぶべき点がたくさん見つけられました。
最後に、台湾で教えている先生方の実際の授業の映像を見ながら授業分析を体験し、教師が日常的に使用している言葉や行動を「意識化」することの重要性について考えました。ビデオとそれに付随する授業のスクリプトを見ながら、良い点や悪い点、どうやったら改善できるか、この場面ではどのようなティーチャートークや指示が適切かなど、グループでの話し合いは尽きることがありませんでした。今回の研修会では、他の教師と授業を共有して、「研究」という形で公開し、意見・情報を交換し合うことがより良い授業につながることがよくわかり、これからも、自分の授業を振り返り、日々よりよい授業をするための試行錯誤を繰り返すことが大切だと実感した研修会でした。
(研修会の様子)
横溝紳一郎先生 柳瀬陽介先生

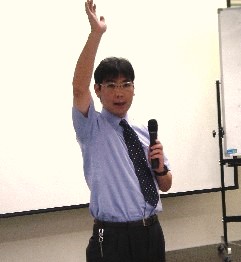
グループでの話し合いの様子
